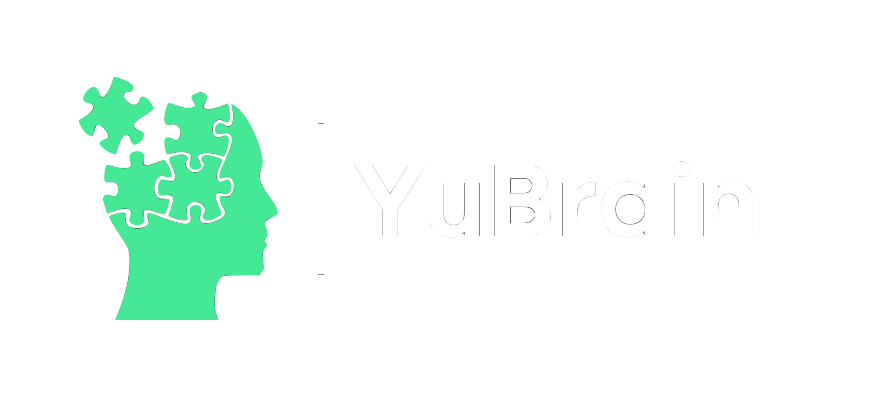Tabla de Contenidos
化学反応が起こると、熱の形でエネルギーを放出することができ、発熱と呼ばれるか、エネルギーを吸収する必要があり、この場合は吸熱と呼ばれます。これらのタイプの反応の最も一般的な例は、燃焼と光合成です。
吸熱および発熱化学反応
化学反応は、原子間の化学結合が壊れて新しい結合が形成されるプロセスです。化学反応には、反応を起こす物質である反応物と、化学反応によって得られる物質である生成物が関与します。
エネルギーがどのように関与するか、つまりエネルギーが吸収されるか放出されるかに応じて、化学反応はそれぞれ吸熱または発熱になります。
吸熱反応とは
endothermic という言葉は、ギリシア語で「内側」を意味する「 endo」と「熱」を意味する「 thermos」に由来します。したがって、エネルギーを吸収する反応を指すために化学で使用されます。これらの反応は自発的に起こるのではなく、エネルギーの投入を必要とします。
吸熱反応がエネルギーを吸収すると、反応中に温度が低下します。それらはまた、熱量を示す大きさであるエンタルピー (+ ΔH) の増加によって特徴付けられます。
吸熱反応の一般的な例は光合成です。この過程で、植物は光エネルギーを吸収し、二酸化炭素と水を植物の栄養素である酸素とブドウ糖に変換します。1 キログラムのグルコースを生成するには、この反応に大量のエネルギーが必要であり、そのエネルギーは太陽光によって供給されます。
発熱反応とは
単語 exothermic は、ギリシャ語の語根exoに由来し、「外側」を意味し、 thermos は「熱」を意味します. 発熱化学反応は、熱の形でエネルギーを放出します. 爆発の場合、運動エネルギーも放出されます。
発熱反応は自然に発生する可能性があります。同様に、エントロピーは高く (ΔS > 0)、エンタルピーは低くなります (ΔH < 0)。発熱反応は爆発的なものになることもあります。
一般的な発熱反応の例としては、マッチや薪に火をつけたときに発生する燃焼があります。
吸熱・発熱反応の例
吸熱反応の例は次のとおりです。
- 塩化アンモニウム (NH 4 Cl) の水溶液。
- 液体水の蒸発。
- 氷を溶かします。
- 水が水素 (H) と酸素 (O) に分解されること。
- オゾン生成 (O 3 )。
- 二酸化炭素 (CO 2 ) の炭素と酸素への分解。
- 熱の作用によるタンパク質の分解。
- 炭酸カルシウム (CaCO 3 )の分解。
- 塩化水素 (HCl) とアルミニウムとの反応による水素の生成。
発熱反応の例は次のとおりです。
- 食卓塩を作るためのナトリウムと塩素の混合物。
- 木材、石炭、石油の燃焼。
- テルミット反応。
- 酸と塩基の混合物。
- 呼吸。
- 核分裂。
- 金属の腐食。
- 酸を水に溶かします。
- 水蒸気の凝縮。
- 金属とハロゲンまたは酸素との反応。
吸熱・発熱反応実験
吸熱反応と発熱反応がどのように発生し、どのようにエネルギーが熱の形で吸収および放出されるかをさらに理解するために、次の実験を実行できます。
吸熱反応実験
お酢で実験
材料
- 酢またはレモン汁
- 重炭酸ナトリウム
- ビーカー
- 実験用温度計
準備: ビーカーに少量の酢を入れ、温度計を挿入します。温度が安定するまで 5 分間待ちます。次に、重曹を小さじ1杯加えます。混合物がどのように熱を吸収し、温度を下げるかを観察します。
塩酸実験
この実験を行うには、材料の取り扱いに注意することが重要です。
材料:
ムリア酸(塩酸) 25%
重炭酸ナトリウム
実験用温度計
準備: 容器に少量の塩酸を入れます。重曹を小さじ数杯加えます。熱を吸収し、温度を零下数度まで下げる反応がどのように起こるかを観察します。
発熱反応実験
泡実験
- 材料:
- 過酸化水素 (H 2 O 2 )
- ヨウ化カリウム (Kl)
- 丼鉢
- 準備:まず容器に過酸化水素水を入れます。次にヨウ化カリウムを加えます。数秒待って、化学反応がどのように進行するかを観察します。
化学反応は一定の速度で進行します。これを反応速度論と呼びます。一部の化合物は、反応速度を上げたり遅くしたりできます。これらの物質は、それぞれ触媒と阻害剤と呼ばれます。過酸化水素とヨウ化カリウムを混合することにより、過酸化水素の分解反応が始まりました。その結果、酸素の泡が発生します。
ホットアイス実験
- 材料:
- お酢
- 重炭酸ナトリウム
- 鍋
- ふた付きガラス容器(耐熱)
- 皿
- 準備: 0.5 リットルの酢に大さじ 2 杯の重曹をゆっくりと加えます。この混合物は発泡効果を生み出します。発泡が終わったら、混合物を鍋で適度な温度で1時間、液体の表面に地殻が形成され始めるまで沸騰させます。火からおろし、残りの液体(現在は酢酸ナトリウム)をガラス容器に注ぎます。しっかり蓋をして冷蔵庫で半日冷やします。鍋の縁や底に残った結晶をスプーンでこすります。それらをプレートに置きます。30分後、ガラス容器を冷蔵庫から慎重に取り出し、蓋を開けます。プレートからいくつかの結晶を取り出し、液体に注ぎます。液晶が結晶化して熱くなる様子を観察します。
酢と炭酸水素ナトリウムを混ぜると、二酸化炭素が泡となって放出され、酢酸ナトリウムが液状になる反応が起こります。混合物が沸騰すると、水が蒸発し、54°C 未満で凝固する溶液が残ります。混合物を急速に冷却することにより、凝固点以下であっても溶液は液体のままです。不安定な状態にあるため、結晶を投げるなどの干渉によって分子の秩序が変化し、結晶化し、熱が放出されます。これにより、ホットアイスの効果が得られます。
参考文献
- 作者いろいろ。化学を教えます。物質から化学反応まで。(2020)。スペイン。編集グラオ。
- Sykes、P.有機化学における反応メカニズム。(2009)。スペイン。エディトリアル・レヴェルテ。
- Levenspiel, O. Engineering Chemical Reactions . (2009)。スペイン。エディトリアル・レヴェルテ。